
ピンク色の粘液便が出ます
22歳・女性の健康相談
3日ほど前から粘液便が出ます。 慢性的な腸炎で過去に何度か粘液便が出たことはありますが色は茶色で肛門部の痛みはなく、今回の粘液便は色がピンクで排便後肛門部に痛みがあります。 お腹がゴロゴロ言っていて、おならが水っぽいぶちゅぶちゅした音で排便もぶちゅぶちゅした音とピンクの粘液便のみで便自体は出ません。 腹部全体に痛みがあります。 関係があるかわかりませんが首が非常にずきずきと痛くそこから頭痛が来ており目が半分しか開きません。 体に気だるさがありぐるぐる回るような目眩がします。 接骨院に通っており定期的にほぐしてもらっていますが、首の痛みが治ることがありません。 上に書いた痛みレベル3は肛門についてで、首の痛みレベルは7程度です。
相談日:2019/06/01
bookmarks同じ悩みを感じたことがある4
相談者が感じているその他の症状
起きられない・いつも眠い 生活時間が不規則 だるい・倦怠感がある 脱力・体の力が入らない 疲れやすい 慢性的な頭痛・頭重 目が開かない おならが出る 腹部全体が痛い 下痢をしている(急性) 排便時に痛みがある 血便が出る (全てをみる)この相談者が異常を感じている部位
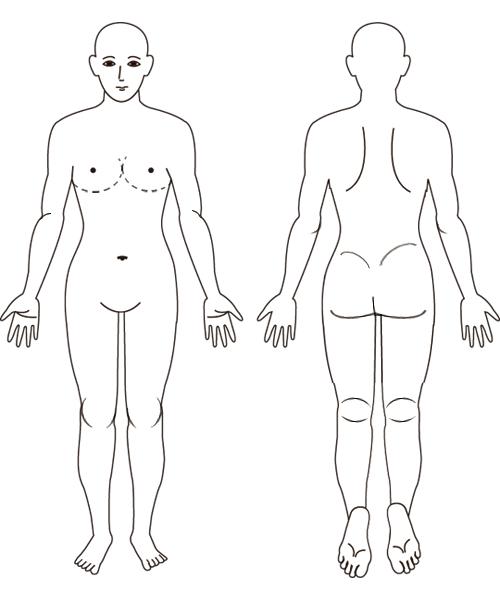
この相談の目的
セカンドオピニオン
大きな病院にいくべきなのか分からない
女性・22歳
身長 157cm・体重 56kg
食欲:ある
顔色:ふつう
症状が始まった時期:2-3日前
この健康相談に対して、2名の医師からの回答がありました
1件目の回答
最寄りの医療機関を受診しましょう
内科医師からの回答
その他の標榜診療科:糖尿病内科(代謝内科), 消化器内科(胃腸内科)

粘血便が出る病気にはいろいろあります。 感染性腸炎 発熱がなければ違うと思います。 潰瘍性大腸炎 可能性が一番高いと思います。消化器内科で大腸内視鏡をしてもらえばすぐにわかります。適切な治療が必要です。 クローン病 潰瘍性大腸炎と似ていますが、小腸だけの場合は診断が難しい場合がありますが、消化器内科を受診してください。適切な治療が必要です。
thumb_up参考になった4
推奨診療科と医療機関タイプ
消化器内科可能性のある病気
クローン病
炎症性腸疾患
出血性大腸炎
潰瘍性大腸炎
※この病名は、相談者から一方向的に送信された相談内容に基づき、回答者である医師があくまで「可能性がある」と感じた病気・疾患名であり、正式な診断ではありません。あなた自身の体調について気になる点がある場合、本サイトのコンテンツのみで判断せず、必ず医師の診察を受けて判断してください。
特に気をつけること: 消化のいいものをとるよう気を付けてください
参考とするWebサイト:
2件目の回答
最寄りの医療機関を受診しましょう
内科医師からの回答
その他の標榜診療科:糖尿病内科(代謝内科)

質問、有難うございます。 内容を拝見すると、「炎症性腸疾患」と「関節炎」を疑います。 両方とも、関連ある症状と思いますので、血液検査・大腸カメラが必要と思います。 内科・消化器内科を受診して下さい。
thumb_up参考になった4
可能性のある病気
炎症性腸疾患
※この病名は、相談者から一方向的に送信された相談内容に基づき、回答者である医師があくまで「可能性がある」と感じた病気・疾患名であり、正式な診断ではありません。あなた自身の体調について気になる点がある場合、本サイトのコンテンツのみで判断せず、必ず医師の診察を受けて判断してください。
特に気をつけること:
参考とするWebサイト:
この相談と関連する他の症状
病院なびで医療機関を探す
-
消化器内科の病院・クリニック
内科の病院・クリニック
「めまいがする」の症状を診てくれる病院・クリニック
「立ちくらみがする」の症状を診てくれる病院・クリニック
「眠い・過眠」の症状を診てくれる病院・クリニック
「だるい」の症状を診てくれる病院・クリニック
「脱力・体の力が入らない」の症状を診てくれる病院・クリニック
「疲れやすい・疲れる」の症状を診てくれる病院・クリニック
「頭が痛い」の症状を診てくれる病院・クリニック
「首が痛い」の症状を診てくれる病院・クリニック
「腹痛・お腹が痛い」の症状を診てくれる病院・クリニック
「下痢をしている(急性)」の症状を診てくれる病院・クリニック
「血便が出る」の症状を診てくれる病院・クリニック
医療Q&Aなびでは、病院なび医療相談サービスに一般の皆様から寄せられた健康・医療に関する相談に、医師が回答した内容をコンテンツとして公開しています。医師が適切な回答を提供できるよう取り組んでおりますが、公開されている内容は相談者からインターネット経由で寄せられた内容のみに基づき医師が回答した一事例です。
通常の診察で行われるような、相談者の感じている症状・状態の詳細の聞き取りや観察などのコミュニケーションに基づく正式な診断ではなく、あくまで「一般的な医学的情報」を提供しています。 あなた自身について気になる症状がありましたら、当サービスのコンテンツのみで判断せず、必ず医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。
なお、当サービスによって生じた如何なる損害につきましても、運営元である株式会社eヘルスケアはその賠償の責任を一切負わないものとします。
