
水いぼ処置でピンセット処置以外を行ってくれる病院を探しています。
6歳・子ども(男子)の健康相談
H30.1〜2頃 水いぼの数が多くなってきたので、受診、麻酔テープを貼り、ピンセットで取る処置をした。 その後 1ヶ月以内に 大きく酷いニキビのようなものができ、痛がり受診。 アクアチムを処方される。 初めに出来た水いぼとは違い、それから 出来る水いぼはニキビなようなものが出来始める。 数もどんどん増えている。 最近顔にも出来始めた為 別の病院への受診を希望。ただし、ピンセット処置ではなく、注射や薬 等の処置をしてくれる病院希望。 2件電話してみたがいずれもピンセット処置のみとのこと。 処置時 病院中に響き渡るくらい泣き叫び、酷く痛がり、暴れ大変だった。 部分麻酔での処置が可能ならそうしてもらいたいくらい可愛そうだった。 本人もピンセット処置は絶対に受けたくないとの事。 生まれた時からアレルギー体質で、アトピー性皮膚炎の傾向があり、今は塗布面積は減りましたが、ずっとステロイドとロコイド混合のものは使用しています。 ヨクイニンが効果的と聞きましたが、本当でしょうか。 よろしくお願い致します。
この相談者が感じている症状
皮膚にできものがあるこの相談者が異常を感じている部位
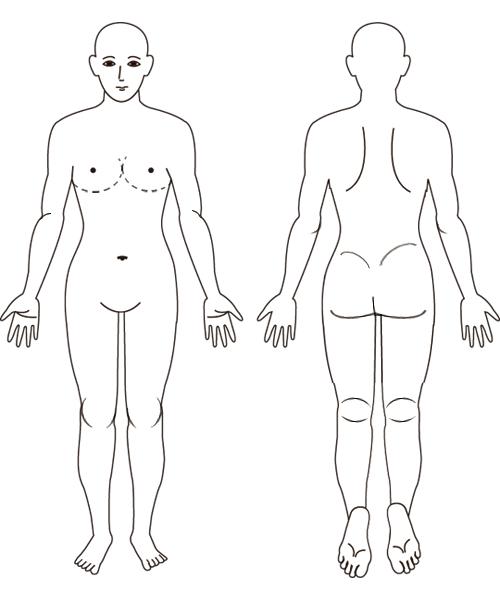
この相談の目的
最寄りの医療機関を受診しましょう
糖尿病内科(代謝内科)医師からの回答
その他の標榜診療科:内科, 腎臓内科, 消化器内科(胃腸内科), 循環器内科

ひとつの方法として小児科専門病院(〇〇こども医療センターや小児医療センターという名前の病院です)の皮膚科をご受診いただくという考え方もございます。このような施設はお子様の対応を得意としております。全国的にも数は多くないのですが、もし通院できる範囲にございましたらご検討いただけますと幸いです。
推奨診療科と医療機関タイプ
小児皮膚科可能性のある病気
※この病名は、相談者から一方向的に送信された相談内容に基づき、回答者である医師があくまで「可能性がある」と感じた病気・疾患名であり、正式な診断ではありません。あなた自身の体調について気になる点がある場合、本サイトのコンテンツのみで判断せず、必ず医師の診察を受けて判断してください。
最寄りの医療機関を受診しましょう
循環器内科医師からの回答
その他の標榜診療科:内科

水いぼは自然治癒するので放置可との意見もあります。切除する場合液体窒素で切除する場合もあります。相談者の居住地域が不明ですので具体的病院名はあげれません。
推奨診療科と医療機関タイプ
皮膚科可能性のある病気
※この病名は、相談者から一方向的に送信された相談内容に基づき、回答者である医師があくまで「可能性がある」と感じた病気・疾患名であり、正式な診断ではありません。あなた自身の体調について気になる点がある場合、本サイトのコンテンツのみで判断せず、必ず医師の診察を受けて判断してください。
最寄りの医療機関を受診しましょう
皮膚科医師からの回答
その他の標榜診療科:アレルギー科, 美容外科

タコに使うスピール膏を貼付して、それでとれる水いぼもあります。試してみてもいいかもしれません。
推奨診療科と医療機関タイプ
皮膚科可能性のある病気
※この病名は、相談者から一方向的に送信された相談内容に基づき、回答者である医師があくまで「可能性がある」と感じた病気・疾患名であり、正式な診断ではありません。あなた自身の体調について気になる点がある場合、本サイトのコンテンツのみで判断せず、必ず医師の診察を受けて判断してください。
この相談と関連する他の症状
病院なびで医療機関を探す
医療Q&Aなびでは、病院なび医療相談サービスに一般の皆様から寄せられた健康・医療に関する相談に、医師が回答した内容をコンテンツとして公開しています。医師が適切な回答を提供できるよう取り組んでおりますが、公開されている内容は相談者からインターネット経由で寄せられた内容のみに基づき医師が回答した一事例です。
通常の診察で行われるような、相談者の感じている症状・状態の詳細の聞き取りや観察などのコミュニケーションに基づく正式な診断ではなく、あくまで「一般的な医学的情報」を提供しています。 あなた自身について気になる症状がありましたら、当サービスのコンテンツのみで判断せず、必ず医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。
なお、当サービスによって生じた如何なる損害につきましても、運営元である株式会社eヘルスケアはその賠償の責任を一切負わないものとします。
